【開催レポート!】2024年度 第2回 学校推薦型選抜オンライン説明会―現役推薦生と交流しよう
![]() 学校推薦型選抜(推薦入試)
2024.12.27
学校推薦型選抜(推薦入試)
2024.12.27
2019.03.02
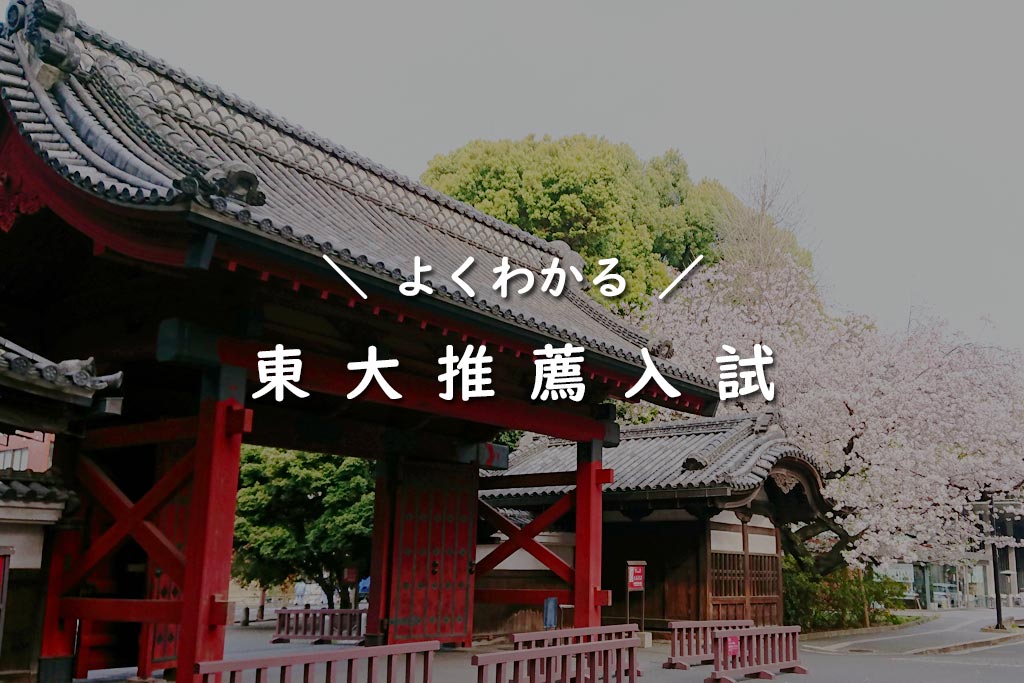
東京大学の推薦入試の狙いと魅力
2016年度からスタートした東京大学の推薦入試(※)。概要については全学ウェブサイトや大学案内にも記載されていますが、東京大学がどのような思いで推薦入試を始めたのか、推薦入試で入学した学生は、前期日程試験で入学した学生と何が違うのかといったことについて、さらに詳しく知りたい人も多いはず。そこで、推薦入試の導入経緯、目的やその特徴、意義について、東京大学高大接続研究開発センター入試企画部門の濱中淳子教授に、2回にわたって伺います。
(※現在、推薦入試は学校推薦型選抜に、また大学入試センター試験は大学入学共通テストへと名称変更)



――東京大学は言わずと知れた、全国でも「偏差値」の高い大学です。入学者選抜も良質な学力試験を課し、その点数で決めるという方法を久しくとっていたわけですが、2016年から推薦入試を導入したと聞いて、驚いた方も多いと思います。なぜ、学力試験以外の方法である推薦入試を始めることになったのか、その背景について教えてもらえますか。
まず、東京大学が受け入れたいと期待する学生像というのは「高い学力を身につけた学生」であることに違いはないのですが、もう一歩踏み込むと「総合的な学力を獲得した学生たち」というところに大きな特徴があります。
東大の入試は、大学入試センター試験の後、前期日程試験によって合否が決まるわけですが、その試験科目は文系でも国語、外国語、地歴(2科目)にくわえて数学があり、理系でも数学と理科(2科目)にくわえて外国語と国語があります。ですから文科、理科と分かれていても、文理どちらの力も見る総合型の試験を課しています。
言い方を変えると、東京大学を志望するみなさんには、入学するまでに総合的に学力を伸ばしてもらいたいと思っていて、それが入試のあり方に反映している。まずは、そのことをお伝えしておく必要があるかと思います。
――偏りのあるタイプではなく、全科目にわたって、高い学力を身につけた学生を求めてきたということですね。
というのも、本学に入学した学生は、まず前期課程(教養学部)に入り、2年間幅広く教養科目を学ぶことになっているからです。そして3年以降、2年次の「進学選択」で決まった学部学科に進み、専門性を極めていくことになります。「レイト・スペシャリゼーション(Late Specialization)」と呼ばれる教育システムです。
ほかの多くの大学が受験時に法学部、経済学部……と学部や学科を決めて入学し、その道を歩みを始めるのに比べて、東大は入学した後に専門を決める。これが他大学には見られない、東大ならではの特徴なのです。
――リベラルアーツ教育を重視しているところに東大の特徴があるということですね。
はい。ただ、総合型という学生像をメインに据えながらも、一方で学生の多様化も重視する。ここが、推薦入試を理解するポイントになります。



――偏りが生まれるのは、ある面では仕方がないことのようにも思えますが、なぜ多様化が重要なのでしょうか。
東京大学がこれまで担ってきた学術的役割は強調されるべきものですが、そのうえで申し上げれば、優れた学問や研究は、多様なメンバーが関わってこそ実現するという側面があります。さまざまなものの見方や価値観、知識を持ち寄ってこそ、知は発展します。
そして、この「多様性が大事」というのは、何も教員だけがそうであればいいという話ではありません。学生たちも、そこに多様性があれば、お互い刺激し合えることになるわけです。教員と学生との間の相互作用も活発になり、多様性が確保されることによって「わくわくする環境」が生まれるんですね。
ところが、近年、東京大学では学生の画一化がみられます。具体的に言えば、首都圏出身者が半分、私立高校卒が3分の2、男子が8割という状況で、この3つの偏りが課題になっています。東大としてもこの偏りをなくし、多様化を進めるための試みの1つが、推薦入試導入ということになります。
――多様化を促進するためにこれまでどのような対策がなされてきたのでしょうか。
推薦入試が始まるまで行われていた「後期日程試験」のことまで遡って説明するほうがいいかもしれませんね。
1980年代末、入試で分離・分割方式がとられるようになってから、本学でも「前期日程試験」「後期日程試験」の2つの入試を行っていました。学生の多様化を目指す本学としては、「後期日程試験」の試験問題を「前期日程試験」のそれとは違うものにということを強く意識して、タイプの異なる問題を出題することで、多様性を図ろうとしていたわけです。
ただ、いくら試験問題を工夫しても、「後期日程試験」の実施時期までは変えられないというところに大きな悩みがありました。当然ですが、「後期日程試験」は、「前期日程試験」の後に実施されるため、「後期日程試験」を受験するほとんどの人たちが、「前期日程試験」を受け、そこでは合格しなかった人たち、という構図になっていたんです。
――「後期」で多様化を狙ったにもかかわらず、そこで合格した人たちは「前期」受験者と変わらない層だったということでしょうか。
そうですね。「前期日程試験」「後期日程試験」の方法だと、受験者層の多様化をもたらすまでに至らないわけです。加えて別の課題もありました。つまり、少なくない「後期日程試験」の合格者たちが、「前期日程試験に合格できなかった」という、持たなくてもいいコンプレックスを持つということが起きてしまったのです。
本来、「後期日程試験」で合格した人は、「前期日程試験」とは性格の異なる試験をクリアした学生であって、そのことを誇りに思って入学してもらいたいわけです。でも、入試が実施される順番が「前期」⇒「後期」となっているために、望ましくない力学が働いてしまったんですね。
こうした問題を解決しようと、はじめは「後期日程試験」という枠組みを維持した中での改革が試みられました。たとえば、科類ごとに問題を別にしていたのを文系と理系の2グループに分けて、グループ間は共通問題にするといったことなどです。
ただ、それだとなかなか大きな変化が生まれない。そうした中で、濱田純一前総長が「もっと根本から見直そう」と決断し、さまざま可能性を視野に含めながら議論を重ねた結果、多様化という問題をクリアするには「前期日程試験」よりもさらに前に、「前期日程試験」とは異なる入試を行うのがいいのではないかと。それによって従来の総合型とは違う強みを持つ学生を取り、多様化を図ろうという判断にいたったわけです。
――試験の時期を「前期日程試験」より前に持ってくることに決めたことと、それが推薦入試になったことには何か関係があるのでしょうか。
まず、日本の入試制度上の問題です。「前期日程試験」よりも前の時期に実施する方法は、「推薦入試」と「AO入試」の2つしかありません。そのどちらかを選ぶことになるのですが、「AO入試」は自分で自分を推薦するものですから、明確な基準が設定しづらい面があります。やはり高校の先生方の協力のもとで、しっかりとした新しい選抜に取り組みたい。このように考え、推薦入試という方法をとることになりました。
改めて申し上げれば、「時期」と「大学と高校とのつながり」という2つの観点を意識して改革を行った結果が、「後期日程試験」の廃止、「推薦入試」の導入ということになります。



――前期日程試験と推薦入試では、学力試験か否かという点以外の違いはあるのでしょうか?
はっきりとした違いがあります。「前期日程試験」からいえば、それは6つの科類別に学生を選抜するという方法を取っています。受験生も文科一類に出願、文科二類に出願…といったように、各科類に出願しますよね。他方で「推薦入試」は、各学部が入学者を選抜する、いわば「学部入試」の方法をとっています。ですから、各学部が設定した要件や条件にかなうかどうか、そこが鍵となる選抜が行われるわけです。
――科類に入学するのと、学部が決まっていて入学するのとでは、大きく違いますよね。入学後に受ける教育も違ってくるのでしょうか。
そのとおりです。誤解がないように先に断っておきたいのですが、推薦入試で入学した学生は、まず入学した学部にもっとも近いとされている科類(法学部なら文科一類)に所属し、科類に課された前期課程(教養学部)の授業を受けていただきます。その点では、前期日程試験で入学した学生も推薦入試で入学した学生も同じです。ただ、こうした共通点とは別のところに違いがあって、大きく2つの特徴が指摘されるように思います。
1つ目は、学部2年次の「進学選択」を意識しない自由な学びができるという点です。学部や学科が決まって入学するわけですから、自分が望む学部や学科に、赤点さえとらなければ進学できるわけです。言ってみれば、プレッシャーを感じることなく、学びを進めることができるので、このことを魅力的に感じる推薦入学者も少なくないのではないでしょうか。というのも、前期日程試験で入学した学生の中には、教養課程の成績が思うようにとれず、希望の学部や学科に行けない人も出てきます。人気の学部学科は希望者も多く、最終的には成績で振り分けられますからね。
2つ目は、「早期専門教育」が施されるということです。先ほど、東大の特徴は、レイト・スペシャリゼーションだと申し上げましたが、推薦入試で入学した学生には、前期課程(教養学部)のときから、教養教育と並行して専門に触れる機会が提供されます。学部にもよりますが、履修の前倒しができたり、夏季休暇期間には研究室で何らかの体験をしたりといったことが行われます。その点で、3年生から専門課程に入るほかの学部生とは大きな違いがあります。さらに、1年次からアドバイザー教員がつき、個別に助言・支援を受けるなど全面的なバックアップ体制が用意されています。
――多様化を狙ったのはわかりますが、早期専門教育という大きな改革まで同時に行ったのは、何故なんでしょうか。
レイト・スペシャリゼーションは本学の大きな強みだとは思うのですが、高校生の中には、自分が進みたい道ははっきりしているのだから、少しでも早く専門のことをやりたい、早く先の授業を聞きたい、先輩たちと一緒に研究室に入って何か体験してみたいという人もいるはずです。そういう人たちからすれば、東大で早期専門教育が受けられるというのは、大きな魅力だといえるように思います。東京大学としても「行きたい学部や学科に進学できるかどうか、進学選択のふたを開けるまでわからない」「専門を学ぶまでに時間がかかる」という理由で東大進学を選択肢から外してしまう優秀な高校生がいるとすれば、それは避けたいところでもあります。
――東大の推薦入試は、学部によって多少の違いはあるものの、基本的には志望理由書と面接が核になっていますが、個人の高校時代の活動や研究を評価するというのは、東大の歴史を考えると、思い切った内容だなという印象があります。
高校生たちの中には、高校時代から、あるいはもっと前から、自分の関心に沿って一生懸命動いている人たちがいます。通っている学校の学習活動に精を出す人もいれば、部活動、あるいは学校を離れた場でいろいろ取り組んでいる人もいます。さまざまなプログラムを利用して海外に行って何かを調べてくるとか、ボランティアを体験するといったことに挑戦している高校生もいます。科学オリンピックなどへの挑戦、「○○甲子園」といった大会に情熱をかける高校生もいます。
このような活動に取り組んできた人たちにとって、推薦入試は自らの行動の記録を発表する場にもなるわけです。実際に推薦入試で合格した学生も「自分が高校時代にやってきたことがどういうことだったのかを振り返られるチャンスになりとてもいい経験でした」とよく話されています。
高校生にとっては、自分が高校で取り組んできた体験が評価されることは自信にもなりますし、自分の関心を貫いて、時間や情熱を注いできてよかったと感じてもらえるのではないかと思います。


――とはいえ、東大が推薦要件として提示している事例を見ると、結構ハードルは高いように感じるのですが…。
「○○オリンピック」という要件が独り歩きをしているように見受けられますが、先ほども言いましたように、東大の推薦入試は、いわゆる「学部入試」です。学部によって要件はさまざまであって、また、「○○オリンピック」というのは、わかりやすい事例として挙げただけだというところがあります。事例として挙げたことのインパクトを払拭したいという学部が、推薦要件の表現を修正するということも行っています。関心のある方は、ぜひ、募集要項を一度丁寧に読んでみてください。そして、「自分がやってきたこと」と「関心のある学部が要項に書いていること」を照らし合わせて、可能性を探ってみてほしいと思います。
学校長の推薦が必要な推薦入試ですが、自分から「私を東大に推薦してください!」と学校に掛け合ってもいいわけです。「我こそは」と思う全国の高校生にチャレンジしてもらいたい、というのが東京大学の思いです。
定員枠の小ささに不安を感じ、躊躇する人もいるようです。たしかに推薦入試の定員枠は全体で100人程度、それを各学部に割り振っていますから、学部によっては数名というところもあります。
しかし、自分でハードルを作ってあきらめる前に、まずは、高校の先生などに相談して、可能性を探っていただきたいし、意欲を持ってチャレンジしてもらいたいと私たちは思っています。
後半では東大の推薦入試ではどんな試験が行われるのか、各学部はどんな学生を求めているのか、推薦で入学した学生たちはどんな人たちなのか、その実際についてご説明します。(よくわかる東大推薦入試(2)はこちら)