基礎実験
![]() 教育プログラム/学びのシステム
2022.04.13
教育プログラム/学びのシステム
2022.04.13
2022.04.11
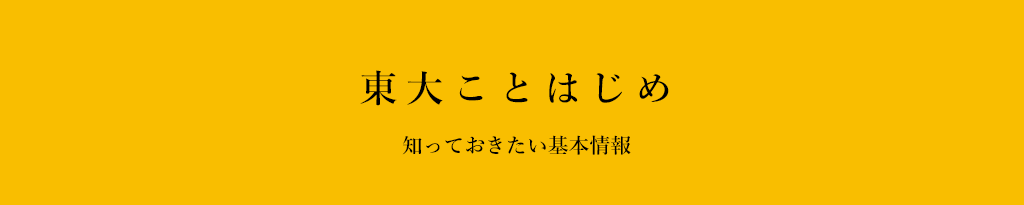
「学術フロンティア講義」という講義名から何を思い浮かべますか?なにか最先端の研究っぽいことをやっているイメージでしょうか。
「学術フロンティア講義」とは、主題科目の一つで、1つのテーマについて、文理双方の教員から構成し、異なる切り口を提供するオムニバス講義です。これだけだとピンとこない方も多いかもしれません。実際にはどのような授業なのか、私が履修した「歴史史料と地震・火山噴火」という授業を例にとって説明します。
地震学や火山学の世界では、地中の構造を調べたり、地球の物理・化学的な性質を調べて、過去におきた地震や火山噴火を知ろうとすることが主流とされていました。理系っぽい内容ですよね。一方、歴史学の世界では、文献調査によって昔の地震や火山噴火の発生を把握していました。こちらはいかにも文系らしい内容です。これらの研究は独立して行うことが主流でしたが、過去の文献に記された記述を読み解くことで、過去の地震や火山噴火の性質がくわしくわかったり、逆に歴史学の側からも別の地域の史料に書いてあった出来事は実は同じものだったといったように、お互い刺激を受け合うことができるということがわかってきたようです。このように、複数の学問分野がそれぞれ異なる角度から協力してアプローチできるテーマ、つまり「領域横断的なテーマ」をこの授業ではとりあげています。「歴史史料と地震・火山噴火」では、地震学・火山学と歴史学それぞれの教員が2名ずつ、オムニバス形式で授業を行いました。
また、「海研究のフロンティア」という講義では、海に関しての最新の知識だったり、海に関する研究の内容や手法の解説が授業内容となっていました。2021年の「学術フロンティア講義」には、「医科学研究最前線」、「Face to face:対面・表面・仮面」などタイトルだけでも興味深い講義もありました。
東京大学では、「学術フロンティア講義」のように、学術の最先端の部分にも触れられる講義が1、2年生でもたくさんあって、自分が興味のある学問を見つけやすいと思います。このような授業を履修して、ぜひ新しい学問の世界に触れてみてください。