基礎実験
![]() 教育プログラム/学びのシステム
2022.04.13
教育プログラム/学びのシステム
2022.04.13
2021.10.12
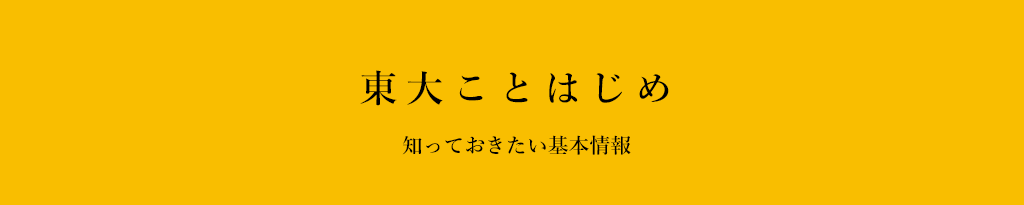
東大生は、ほかの多くの大学生よりも専門を決めるのが1年半ほど遅い。なぜなら、東大の教育は前期課程(1、2年生)と後期課程(3、4年生)で分かれており、リベラル・アーツを学ぶ前期課程での学びをもとに、後期課程で進む学部を選ぶことができるのだ。この入学後に進学先を選ぶことができる制度を 「進学選択制度」という。前期課程教育と進学選択制度については、こちらも参照してほしい。
さて、進路を決めるのが他大学より遅いといっても、前期課程の科類と後期課程の学部にはいくらかの関連がある。下の図は各科類の主な進学先を表したものだ。概ね矢印どおりに進学する学生が多いのだが、努力次第では、ほぼすべての学部に進学することが可能である。

進学選択では、進学先ごとに各科類から受け入れる人数を定め、その定数の枠として「指定科類枠」と「全科類枠」の2種類がある。取得した単位数と成績に基づいて、科類を問わず志望できる「全科類枠」(こちらを参照)を利用することで、すべての科類からどの学部にも進学することができるのが進学選択制度の魅力のひとつである。その一方で、全科類枠での進学は一般的に指定科類枠よりも難しいと言われている。
では、実際にどのような進学例があるか、見てみよう。まずは、筆者自身の例をあげると、私は文科三類から経済学部に進学した。高校生時代、文学や英語が大好きだった私は「文学部の英文科専修に行ってイギリス文学を学びたい!」と文科三類を受験した。しかし、大学で受けた講義の中で経済学が最もおもしろく、方針転換したのだ。私の場合は、東大でなければ経済学を学ぶ機会もなく経済学のおもしろさを知ることもなかったと思うので、非常に制度の恩恵を受けた。
また、文理の垣根すら超えて進路を選択する人もいる。筆者の友人にも、文科三類から医学部健康総合科学科に進学し看護学を学んでいる人がいる。この友人は、国際問題に関心があり教養学部を志望していたが、大学での学びを通して現場で役立つ専門を身につけたいと考えるようになり、医学部への進学を決めたそうだ。
このように、東大の教育体制のもとでは他大学ではあり得ない進路選択をすることができる。前期課程で幅広い学問と出会うことができ、後期課程で学ぶ専門をじっくりと選ぶことができるので、うまく利用すれば自分の進路の可能性を広げることが可能である。
ただし、進学選択制度があるとはいえ、高校生のうちから自分の進路や学びたいことを考えるのは非常に重要だ。入学科類によって進学しやすい学部や前期課程で履修する授業に差が出てくるため、東大入学前から進路について情報収集をすることで入学後のミスマッチを防ぐことができるのだ。普段から進路を見据え、将来への目的意識を持って学べば、より実りの多いキャンパスライフを送れるだろう。