学術フロンティア講義
![]() 教育プログラム/学びのシステム
2022.04.11
教育プログラム/学びのシステム
2022.04.11
2022.04.13
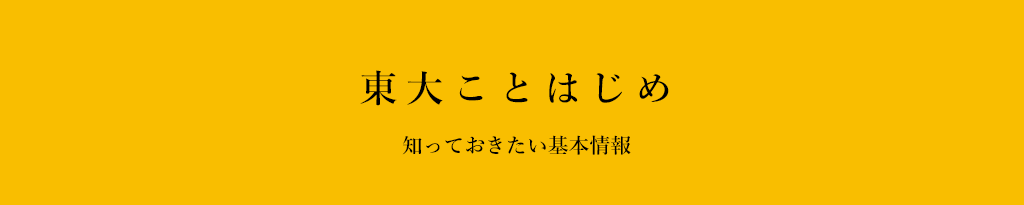
「基礎実験」とは前期課程(1、2年生)の理科生の基礎科目の1つ。理科生は1A~2S1(*)タームの間(1年秋学期~2年春学期前半)、週に1日、2コマを受ける。「基礎実験」はいわゆる必修で(必修なのは2S1タームまでだが、任意選択で2S2タームも基礎実験の科目を履修できる)、理科生はこの単位をとることなく、後期課程(3、4年生)に進むことはできない。
(*)A1・A2は秋学期の中の前後半、S1・S2は春学期の中の前後半のことを指し、その前につく数字は学年を表す。例えば、「2A1」は2年次のA1ターム(概ね9〜11月)のことを指す。
理1と理2・3で、科目の名称や内容、選択の自由度は多少異なるが、科目の特徴は概ね変わらない。つまり、理1の「基礎実験I (物理学)」と理2・3の「基礎物理学実験」など、科目が同じであれば、特徴は大体同じである。筆者は理2生だったので、その経験をもとに物理、化学、生命科学の各実験について紹介したいと思う。
✅「基礎物理学実験」(理1の場合は「基礎実験Ⅰ(物理学)」)
基礎物理学実験では、2人組のペアで実験を行う。予習や設問、考察は全てノートに書き込み、そのノートを提出し評価される。手書きのため、それなりに予復習に時間を要した。また、グラフや表の書き方の作法も習った。理科生はここで、理系としての図表の書き方を覚える。扱っている実験は、交流回路の特性の確認や、オシロスコープを利用した光速度の測定など、どの大学でも行っているものが多いが、他大の基礎実験も受けたことがある身としては、理論を教科書に丁寧に書いてくれており、しっかり予習すれば得られることも多いと感じた。
✅「基礎化学実験」(理1の場合は「基礎実験Ⅰ(化学)」)
基礎物理学実験同様、2人組のペアで実験を行う。教科書の巻末についている、各実験のプリント1枚を提出し評価されるのだが、1枚のプリントに設問や考察を書くので、紙が足りないこともあった。基礎物理学実験に比べて予復習にかかる時間を短縮でき、予習をしっかりし、手際よく実験をこなせば早く帰ることができる。グリニャール反応や計算化学など、大学ならではの実験も行われるので、知識面に不安がある人は化学の復習や「基礎化学」の受講の検討をお勧めする。
✅「基礎生命科学実験」(理1の場合も同一名称)
自分が基礎生命科学実験をうけた2S1(2年次の春学期前半)は、ちょうど、新型コロナウイルス禍の初めての緊急事態宣言が発令され、受講方法はビデオ視聴とそれを踏まえたレポート作成になった。それにより、基礎生命科学実験で行っているウシガエルの解剖が行えず、悲しいようなうれしいような気がした。例年はそこまでキツイ課題ではないらしいが、課題の量が結構あり、トータルでは辛い授業に感じた。内容は植物の多様性から、新型コロナウイルス禍で話題となったPCR検査の原理など、幅広いものになっている。
基礎実験を受講すると、知識を補ったり実験手順を確認したりするための「予習力」や、実験結果に対する「考察力」、結果や考察を文章や図表として「まとめる力」を養うことができる。研究に置き換えると、「先行研究の調査」・「実験の組み立て」や「分析」・「新規課題の発見」、「論文執筆」といったところだろうか。予習やレポートなど大変なことも多いが、東大生の未来の研究活動の「基礎」を作るように設計されており、必ず役立つのではないかと思う。最後になりますが、これから基礎実験を受けられるみなさんに、この記事が少しでも参考になれば幸いです。