「第98回五月祭」レポート2025!-2日目
![]() 駒場祭・五月祭
2025.06.30
駒場祭・五月祭
2025.06.30
2021.01.12
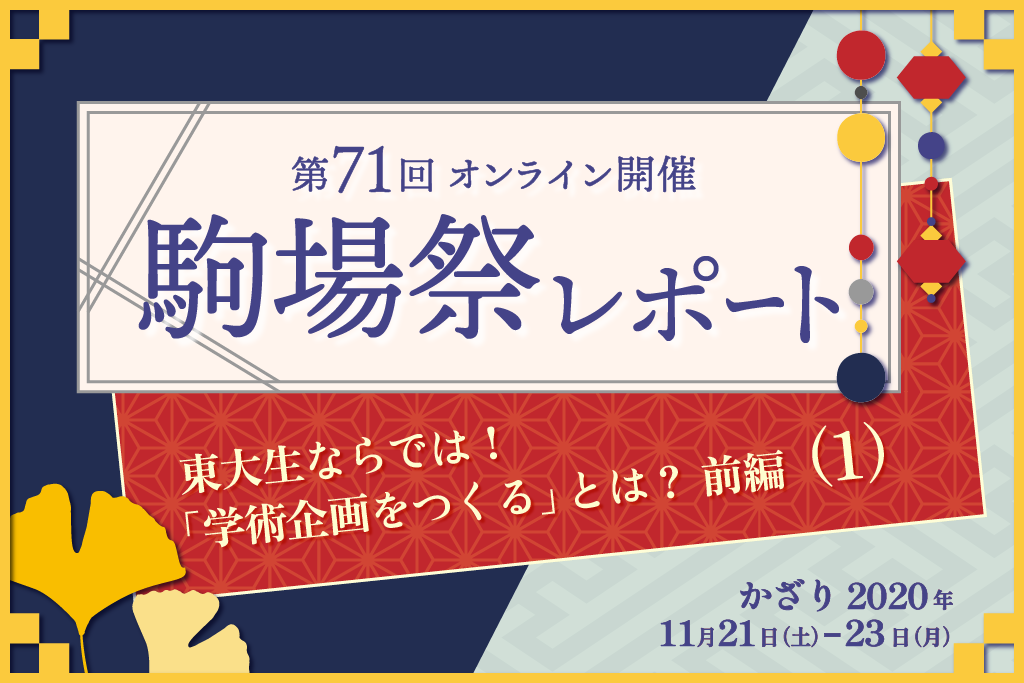
第71回駒場祭の様子をレポート
駒場祭は、毎年1、2年生が主体となって運営し、駒場キャンパスで11月に開催される学園祭です。今年は、新型コロナウイルス禍の影響で五月祭に続き、駒場祭史上初めてのオンライン開催となりましたが、東大生のさまざまな工夫を凝らした魅力的な企画が数多く公開されました。「駒場祭のかざりかた」を合言葉に創意工夫されたお祭りの様子を「キミの東大」学生ライターとともにレポートします。
オンラインだからこその魅力がつまった駒場祭の企画をぜひ楽しんでください。
学園祭と言えば、出店で買い物をしたり、展示を見たり、「遊びに行く」様子を想像する人が多いかもしれませんが、企画を出展する側として学園祭に関われるのも大学生ならでは。特に駒場祭では毎年良質な学術企画が多数開催され、その多くは学生が一から企画・運営を行っています。
今回は、駒場祭で学術企画を出展した学生ライター2名にインタビューを敢行。前編・後編に分けて「学術企画をつくる」魅力をお届けいたします。前編では、模擬裁判を企画・運営した学生ライターに話を聞きました。
出展した企画:模擬裁判2020(法と社会と人権ゼミ)
語り手:加藤友樹さん
――加藤さんは、模擬裁判2020を企画・運営した「法と社会と人権ゼミ」に所属されているそうですね。まずはこのゼミについて詳しく教えてもらえますか?
法と社会と人権ゼミ、通称「川人ゼミ」は、社会の現場で働く方々からお話を伺ったり、実際の現場で体験活動を行ったりすることにより、社会の実態を知り、社会問題について考えるという団体です。もう30年近い歴史があるんですよ。
――「現場から社会を知る」という精神が、先輩から脈々と受け継がれてきたんですね。今回は模擬裁判を劇仕立てにして配信されていましたが、これも毎年恒例の企画なんでしょうか?
はい。毎年ゼミ内の有志で、模擬裁判劇を作り上げて駒場祭に出展しています。出演者は1年生が中心で、前年の出演者である2年生が脚本執筆や演技指導、広報活動などを担当します。
――加藤さんは2年生ですが、今年はどのような役割を担われたんですか?
僕は今年、演技指導責任者と出演者という2つの顔を使い分けていました。
――なんだか、すごく責任のある立場のように聞こえます。
はい。さらに途中から、駒場祭全体の企画運営を行う駒場祭委員会とのやり取りも担うことになったため、やることが多岐にわたって大変でした。
――加藤さんは、9月にオンライン開催された五月祭で「東京大学法律相談所」主催の模擬裁判を視聴して、その様子を「キミの東大」でレポートしてくれましたよね。この時、まさに駒場祭の準備の真っ最中だったと思うのですが、模擬裁判を観覧した経験は役立ちましたか?
私たちの企画はまさにオンライン配信での模擬裁判劇ということで、五月祭で視聴した模擬裁判の配信方法や特有の見せ方、熱の入った演技などはどれも非常に参考になりました。
――先輩たちの試みから学んだことを、自分たちの企画にも活かそうとされたわけですね。
そうですね。撮影班などは、「東京大学法律相談所」の担当の方とやり取りして撮影方法に関するアドバイスを頂くこともできました。演技指導責任者として、とても頼もしく感じました。
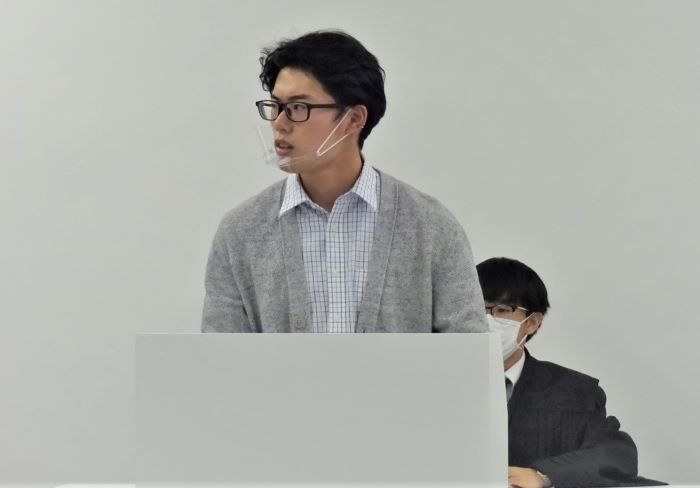
――実際に企画を終えて、どのような感想をもちましたか?
「他の出演者と一緒に劇を作り上げている」という感覚をリアルタイムで味わえて、とても充実していました。また、自分で役を演じてみることによって、実際の当事者の感覚を疑似体験でき、テーマとなっている社会課題をより身近に感じるようになりました。
――今回の模擬裁判ではどのようなテーマに取り組まれたのでしょうか?
今年は「医療過誤と新型感染症」をテーマに模擬裁判劇を制作しました。過去に多くの議論を呼んだ、実際の医療過誤裁判をベースにしています。そこに現代の世相を反映させることを意識して、今世界中を震撼させている新型コロナウイルス感染症を要素として加えました。
――繊細かつ重大なテーマで、観覧した人にとっても考えることの多い企画だったと思いますが、どんな感想を聞いていますか?
「実際の裁判の流れがわかって興味深かった」「当事者の声を聞く重要性が伝わった」という感想は、自分たちがこの裁判劇を通して伝えたかったことの中心部分が伝わっていたとわかるもので、印象に残っています。
一方、「やや感情的なやり取りが多かった」というご指摘も受けました。演劇という企画の特性上、感情に訴えかけることはある程度意識的に行ったものだったのですが、この辺りのバランスの取り方が難しいなと改めて感じました。こういった課題は来年運営してくれる後輩に託したいと思います。
――来年は、後輩の方々がこうした課題に向き合いながら企画を出展することになるのですね。ここまでお話を伺って、難しいテーマに果敢に挑み、多くのことを学んだ様子が伝わってきたのですが、ずばり、駒場祭で学術企画を出展する一番の魅力は何だと思いますか?
「高校までのイベントよりはるかに多様なお客さんを前に、大学生活の成果を自由な形で発表できること」、これが魅力だと思います。
――もしかすると、お客さんの多様性はオンライン開催になることでさらに広がったかもしれませんね。多様な人に成果を発信できた経験を、ぜひ今後の加藤さんの人生にも活かしてくれたらと思います。本日はありがとうございました!