令和6年度 東京大学総長賞受賞者の声(学業編)
![]() 学生表彰
2025.04.04
学生表彰
2025.04.04
2020.05.08

東大総長賞とは?
「本学の学生として、学業、課外活動、社会活動等において特に顕著な業績を挙げ、他の学生の範となり、本学の名誉を高めた者」(個人又は団体)に対して、東大の総長が直々に表彰を行う賞です。賞の授与は平成14年から始まり、年に1回、受賞者の表彰と活動(研究や課外活動、社会活動など)の内容に関するプレゼンテーションが行われています。令和元年度は12の学生・学生団体に対して総長賞が授与されました。
「キミの東大」では、受賞者の方々に活動/研究内容を教えてもらうとともに、高校生のみなさんへのメッセージもいただきました!
ぜひ、東京大学の学生の活動の幅の広さと学びの深さを体感してください。今回は、学業編をお届けいたします。
TABLE OF CONTENTS
【河野 遥希さん】 戦略的情報伝達に関する理論・応用研究
【國頭 真理子さん】 『〈娘役〉のクィアネス 花總まりを例に』
【木戸 照明さん】 こころに時計はいくつあるのか?ヒトの心的時間のアンサンブル特性の研究
【濱崎 甲資さん】 ゲノム育種の最適化に寄与するシミュレーション研究および新規手法の開発
【前田 健人さん】 新たな推定手法の創出による量子暗号の長距離化の研究
【坂上 沙央里さん】 大規模ゲノム情報を疾患基盤の解明・臨床応用に役立てるための新規解析手法の開発と国際共同研究の遂行
【木村 謙介さん】 STM単一分子発光分光法による革新的な励起子形成機構の探索
【鳴海 紘也さん】 物体の相変化に着目した形状変化インタフェースに関する研究

情報の送り手とその情報をもとに意思決定を行う受け手との間で、必ずしも利害が一致しない場合に、どの程度の情報を伝達できるかを明らかにする理論が、戦略的情報伝達の理論です。この理論は、Vincent P. CrawfordとJoel Sobelという2人の研究者が1982年に発表した論文によって生み出され、この論文については極めて多くの研究がなされてきました。私は、彼らの論文の中心となる定理の証明の中で、40年近くの間、研究者たちが直感的に正しいと認めてきた箇所が、数学的に間違っていることを指摘し、私が中心となって2019年に発表した論文では、証明が成立しない例を挙げ、解析学の手法を用いて精密な証明を行いました。この論文は、経済学において最も権威ある雑誌である Econometrica 誌に掲載され、高く評価されました。
卒業論文では、中央銀行と市場との間のコミュニケーションに、戦略的情報伝達の理論を応用することを考えました。中央銀行を情報の送り手、市場の参加者を情報の受け手とみなし、実現しうる均衡を解析したもので、金融政策に関しての情報を中央銀行がどのように公開するべきかを考えるにあたり有益な結果を得ました。また、この卒業論文は、経済学部の特選論文に選ばれています。


卒業論文『〈娘役〉のクィアネス——花總まりを例に』では、宝塚歌劇団(以下、「宝塚」)でトップ娘役を務めた花總まりに注目し、娘役の女性性がジェンダー規範や異性愛のシステムを撹乱するように作用しうることを論じました。
宝塚における娘役は、男役トップスターを中心とするスター・システムとロマンティックラブの成就を原則とした作品群において、「男役に寄り添う」という役割を求められ、可憐さや上品さというイメージを担ってきました。花總まりは、その長いキャリア全体にわたって少女性や「お姫様」性など、この娘役らしいイメージで語られてきましたが、一方で花總のパフォーマンスを見ていくと、必ずしも異性愛的な枠組みが女性に押し付けてきた立場にそぐうものとはいえません。本稿は、映画スター研究の枠組みを借りながら、この「娘役らしい」にもかかわらず、男役中心のジェンダー・システムや異性愛主義的な構造からはどこか逸脱しているという、彼女のスターとしてのイメージを分析し、花總は「娘役でありながら」男役的な立場に踏み込んでいたのではなく、反対に花總は「娘役だからこそ」そのようなパフォーマンスを行うことが可能だったのだと、すなわち「娘役らしさ」を徹底して追求することこそが「男役に寄り添う」という娘役の規範から離れる可能性に花總を導いていたのだと論じました。
この論文は、宝塚批評の枠組みを超えてフェムや少女文化に関する議論も参照しながら、女性性をめぐるジレンマに応答することに成功した点、またパフォーマンス研究とジェンダー研究の二分野を横断し卓越した成果をあげた点を、高く評価されました。

私は、学部3年生の秋から4年生にかけて、脳がどのようにして「時間」という情報を処理しているのか(時間知覚)について研究を進めました。これまで時間知覚研究の多くは、単一の時間情報の処理に焦点をあててきました。しかし、現実世界ではつねに身の回りに複数の時間情報が存在しており、私たちはつねに関心のある時間情報を抽出し、ときにはそれらを統合する必要があります。
そこで、視覚における複数の時間情報の統合に着目し、実験を行いました。様々な時間の長さをもつ複数の視覚刺激を一度に呈示したうえで、実験参加者にそれぞれの時間の長さを統合して平均を再現してもらったのです。その結果、ヒトがかなりの精度で複数の時間情報を統合できることが分かりました。一方で、統合すべき情報が増えることで混入する知覚のノイズ(統合した情報のばらつき)が増すことも判明しています。こうした実験の枠組みが、脳機能計測と組み合わせることで時間知覚だけでなく、情報統合や知覚ノイズ混入に関する神経基盤の探求を可能にするものとして高い評価を受けました。


人口増加と気候変動により深刻化が進む食料問題を解決する鍵として、作物の品種改良を効率的・高速に行う技術が期待されており、ゲノム情報から目的形質(注目している作物の特性・性質)に関与する遺伝子の候補を選ぶ手法であるゲノムワイド関連研究(GWAS)や、作物の遺伝的能力を予測するゲノミック予測とよばれる手法が注目を集めています。濱崎さんは、こうした手法をさらに発展させるべく研究を行いました。
GWASを行う際の最適な解析集団の選択に関するシミュレーション研究では、異なる遺伝的背景からなる混合集団を用いるとGWASによる遺伝子の検出力が向上する可能性を見いだしました。また、これまでのGWAS手法では困難だった複雑な遺伝機構を持つ遺伝子を検出できる新たな手法を開発しました。さらに、ゲノミック予測に関する研究では、ゲノム以外の生体分子に関する情報やドローンなどを用いて計測した作物体の情報をどう利用すべきかを検証し、予測精度と計測コストの両面からゲノミック予測を最適化することに成功しました。こうした一連の成果は、品種改良の効率化・高速化に直接的な貢献が期待できるものとして、高い評価を受けました。

量子暗号とは、量子力学の性質を利用し、通信を盗聴する人の計算能力が高くても安全性(セキュリティ)を担保できる暗号通信方式です。その一つである「ツインフィールド方式」は、他の方式に比べて長距離での通信を効率的に行うことができる方式として注目を集めました。しかし、この方式は送受信方法を大きく変更したため、安全性の証明が従来通りにいかなくなってしまい、現実的な通信時間の運用の中で、効率と情報の安全性をいかに両立するかが未解決問題として残されていました。
前田さんは、盗聴の痕跡を厳密に調べられる「演算子優越法」という統計推定方法を新たに提案しました。そして、それに基づいて安全性を担保するためにユーザーが行うべき手続きを具体的に示しました。もともと、ツインフィールド方式で盗聴者の痕跡を調べようとすると、既存技術では作ることのできない特殊な光が必要となることが知られており、これが障壁となっていました。しかし、「演算子優越法」では、既存技術で利用可能なレーザー光のみを使って、盗聴者の痕跡を調べることができるのです。
研究の結果、ツインフィールド方式の量子暗号は、現実的な通信時間で効率と情報の安全性を両立できることが証明されました。また、前田さんが提案した「演算子優越法」の平易さと汎用性の高さは、他の量子暗号方式の安全性証明への適用や、より広い光量子技術への応用が期待できるものとして、国内外の多くの研究者から高い評価を受けました。


現在、全世界で数百万人規模のゲノム情報が蓄積されており、全ての細胞の設計図であるゲノムの個人間の違い(遺伝的変異)と、私たちの特徴(形質)や将来の病気のリスクとのつながりが網羅的に判明しつつあります。そのような中、遺伝学研究には、①ゲノム情報が複雑な疾患を形作るメカニズムの解明、②ゲノム情報を臨床現場での診療に役立てる方法論の構築、③ゲノム情報・解析人材の欧米偏重の解消、といった世界的な課題があります。
①の課題に対して、坂上さんは、全ゲノムに渡って遺伝的変異と疾患との関連を解析した結果に、ヒトの細胞組織ごとの網羅的マイクロRNA発現データを統合解析し、マイクロRNAが疾患に影響を与えるメカニズムを明らかにする新たな遺伝統計学の手法を提案しました。また、ゲノム情報を活用して、有望な創薬ターゲットを特定したり、すでにある薬剤を他の疾患の治療に役立てるためのソフトウェアの開発を行いました。
また、②の課題に対して、医師としての診療経験も持つ坂上さんは、ゲノムという生まれてから変えることのできない情報を、集団レベルでの健康改善に役立てる方法論に問題意識を持ちました。そこで、個人の形質を遺伝情報から予測する遺伝統計学手法を、多層に渡る臨床情報と統合して解析し、医療介入可能な健康リスク因子を明らかにする手法を提案しました。この手法を日本人17万人のバイオバンクデータに適用したのみならず、イギリス・フィンランドの国家的バイオバンクを含めた計70万人の過去最大規模の解析をリードして、人種に共通な健康リスク因子、人種に特異な因子の特定を行いました。
そして、③の課題に対しては、大規模日本人ゲノム配列データから日本人内部のゲノム多様性を初めて明らかにし、この多様性を理解することが将来の健康リスクの予測に対しても重要であると報告しました。
これらの研究活動の中で、国際学術雑誌に多数の論文を掲載したこと、国際共同研究に主要解析者として貢献したこと、国際的な学会での2度にわたる受賞歴や記者発表といった実績を残したことが高く評価されました。
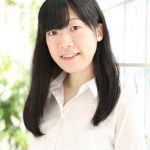
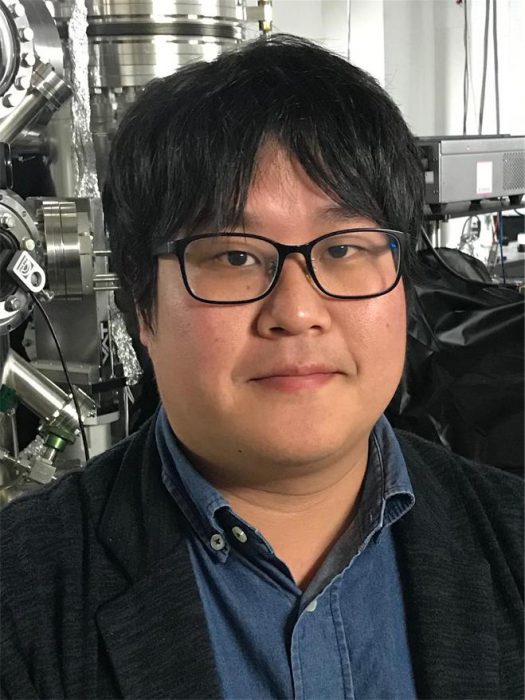
有機分子に電流が流れることで光が生じる有機エレクトロルミネッセンス(有機EL)現象は、スマートフォンの画面に応用されるなど私たちの生活に身近なものです。有機ELの分子発光には、「蛍光」と「りん光」の2種類があります。従来の有機ELでは、「蛍光の発光源」と「りん光の発光源」は1:3で形成されることが知られており、りん光の発光源を効率的に形成することが有機ELデバイス開発において重要な指針です。
木村さんは、ナノメートル(1ナノメートルは10億分の1メートル)というミクロな単位の空間分解能を有する走査トンネル顕微鏡を駆使して、単一分子への電荷注入により生じる発光を観測することに成功し、この「最もシンプルなモデル実験系」で、新たな発光源形成機構を探索しました。走査トンネル顕微鏡が加える電圧を変えながら測定した結果、低電圧ではりん光のみが生じるという、りん光の発光源が選択的に形成されていることを示唆する現象を観測し、さらなる調査で選択的形成が起こるメカニズムも突き止めました。これは、従来の定説であった「蛍光とりん光の発光源形成は1:3則」を破り、りん光の発光源を選択的に形成した結果であるといえ、新たな有機ELデバイス原理の可能性を示すものです。一連の成果は、Nature誌に掲載され、高く評価されました。


人間と計算機を仲介するユーザ・インタフェース(UI)の歴史を振り返ると、より一般のユーザに普及するUIは、文字のようなデジタルな形態よりも、スマートフォンに代表されるタッチインタフェースのようなフィジカルな形態となる傾向があります。人間と計算機とのやりとり(ヒューマン・コンピュータ・インタラクション)が、今後さらにフィジカルな形態に発展する方法はあるのでしょうか。
鳴海さんは、デバイスを構成する素材の物性をインタラクションに利用するヒューマン・マテリアル・インタラクションを提案し、その実例として、デバイスに「相変化」(固体・液体・気体などの変化)する能力を付与した2つの形状変化インタフェースを開発しました。1つはLiquid Pouch Motorsと呼ばれ、通常時は紙のように薄く軽く柔らかいですが、内部に含まれる少量の液体が気体に変わる体積変化によって強く大きく変形するものです。もう1つはSelf-healing UIと呼ばれ、傷が「治る」特殊なポリマーの性質を利用することで、固体・エラストマ(ゴムのように伸び縮みする状態)・液体の性質の「いいとこ取り」を可能とするインタフェースデバイスです。
鳴海さんの研究成果は、複数の分野のトップ学会での発表・受賞にどまらず、国際的なメディアアートの祭典での展示やファッションブランドとの共同制作などへと領域横断的に発展し、高い評価を受けました。

課外活動・社会活動編はこちら