学校推薦型選抜合格者の声 ― 新入生インタビュー 2025
![]() 学校推薦型選抜合格者の声
2025.07.10
学校推薦型選抜合格者の声
2025.07.10
2025.07.10
![]() #経済学部
#経済学部
#新入生
#新入生
#推薦生
#推薦生
#学生インタビュー
#学生インタビュー
#学校推薦型選抜
#学校推薦型選抜
#経済学部
#経済学部
#新入生
#新入生
#推薦生
#推薦生
#学生インタビュー
#学生インタビュー
#学校推薦型選抜
#学校推薦型選抜
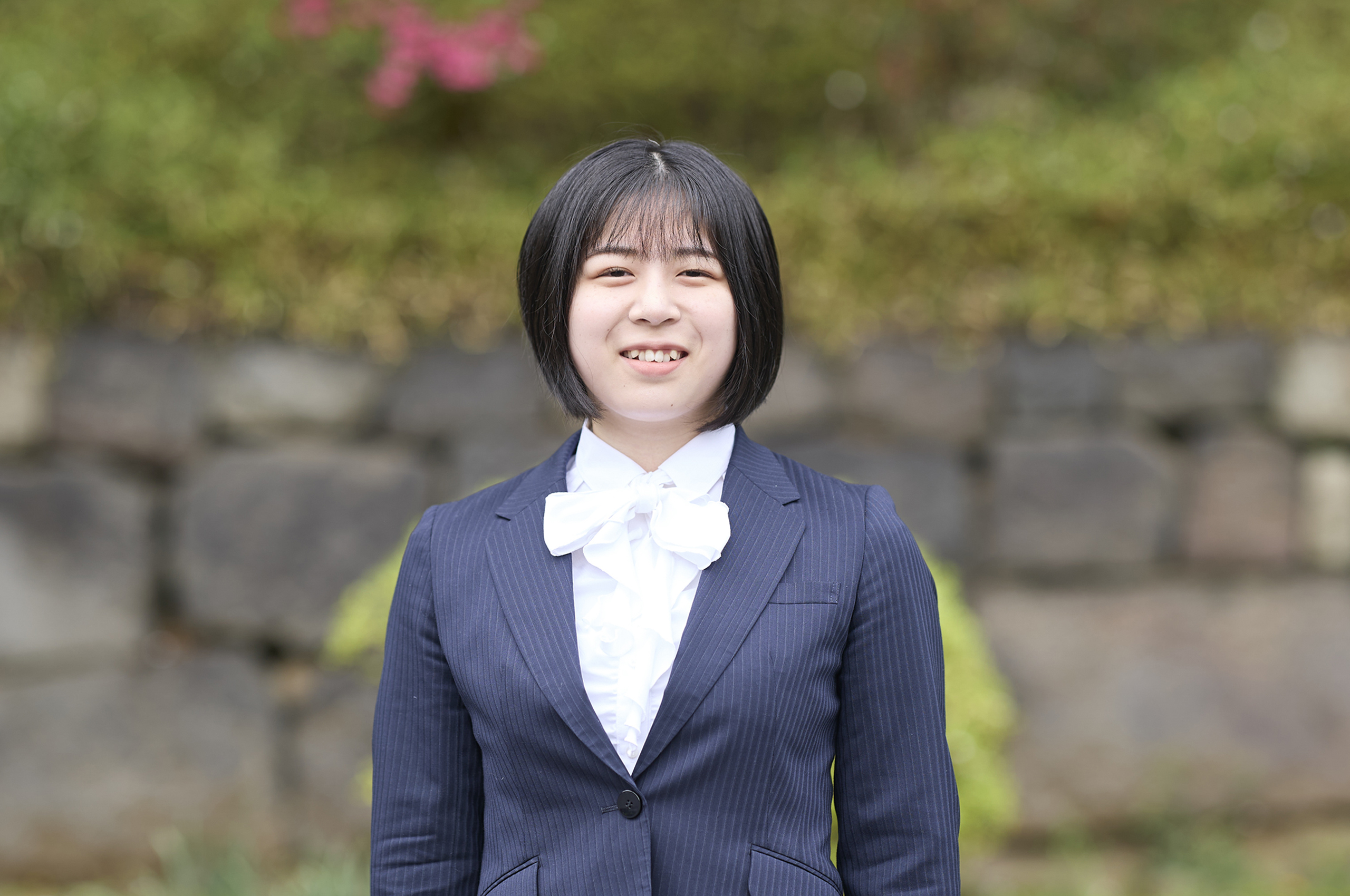
PROFILE
――東京大学を志望した理由を教えてください。
私は、文系の中から自分のアルゴリズム活用能力を活かせるマーケットデザインを学ぶために東京大学の経済学部を志望しました。自分の能力を活かせる分野を探していたときに、東京大学のマーケットデザインセンターの小島武仁教授が研修医と病院のマッチングというかたちでマッチング理論の社会実装に取り組んでおられるのを見つけて、とても刺激を受けました。
――アルゴリズム活用能力は、どのように培われたのでしょう?
日本情報オリンピックに楽しそうに参加していた兄の影響で、小学生の頃からプログラミングに興味をもち始め、予選の過去問を解いたり、わからないところはインターネットの記事を読んだりして、独学で勉強をしてきました。小6から高3までは、実際に私もその大会に参加して、大会前になると平日3時間、休日は10時間以上、問題を解いて準備していました。大会では、実社会を模した問題が出題され、選手は与えられた課題に対して性能の良いアルゴリズムを設計して、それをプログラムとして適切に実装されているかを競い合うんですけど、時間をかけて問題が解けたときの喜びが大きくて、続けてこられた気がします。
――なぜ、マーケットデザインに関心をもたれたのですか?
そもそも、私はアルゴリズムを使って制度設計するものがないと思っていました。でも、マーケットデザインは、情報オリンピックの問題を解いていく過程と発想が逆で、現実の市場をより良く設計するために、アルゴリズムを用いて制度設計しているんです。小島先生の研究では、たとえば、研修医は都市部の病院で働きたい人が多いので、地方の病院にも研修医を呼びたい場合、全体の合理性のために定員を決めるんですけど、都市部で働きたいのに地方に行かなければならない研修医がいたら個人は満足できないので、全体と個人がバランスよく満足できるマッチングのために、アルゴリズムを活用しています。そういったところに興味をもちました。
――学校推薦型選抜に挑戦するにあたって、苦労したことや工夫したことはありますか?
高校2年の冬に、担任の先生から「学校推薦型選抜に挑戦してみないか」と声をかけていただいたんですけど、学校推薦型選抜と一般選抜の両方を視野に入れて考えていたので、高3の9~10月は書類準備、11~12月は面接準備で、一般選抜のための勉強はなかなか手がつけられなくてとても不安でした。そういった心の負担を少しでも軽くするため、同じ時期にどちらも進めるのではなく、どちらかに集中して、気持ちを切り替えてやるようにしていましたね。
――これから東大でどんなことを学びたいですか?
マーケットデザインを学んでいくにあたって、まずは、過去や現在の制度を学びたいなと思っているので、経済史や経済系の制度史を学べるような授業を取りたいです。
――勉強や研究以外に取り組みたいことはありますか?
大学に入ってから新しいことにチャレンジしたいと思っていたので、いろいろな部活やサークルを調べて、その中でも映像を見てアクロバティックな動きが魅力だった躰道部に入りました。
――どのような将来像をイメージしていますか?
マッチング理論やゲーム理論を使って制度設計をするなど、将来はマーケットデザインの分野に取り組んでいきたいと思っています。でも、まだ新しい分野で社会実装例が少ないということもあるので、金融関係など、ほかにも興味がある分野を幅広く学びながら考えていきたいです。
――最後に、高校生に向けたメッセージをお願いします。
学校推薦型選抜をめざしている人は、私のように学部とは直接関係がないように見える実績しかなかったとしても、自分が追求したいものがあれば、ぜひチャレンジしてほしいなと思っています。一般選抜をめざしている人も含めると、私は北海道出身で、入学前まではいろいろ心配していたこともあったんですけど、東大生は割と気さくに話しかけてくれる人が多いので、地方出身であっても臆することなく、東大に挑戦してほしいです。
――素晴らしいメッセージをありがとうございました。これからのご活躍を期待しています!